その他(海外)

『時のみぞ知る』(2013.7.26 tanakomo)
さすがジェフリー・アーチャーって感じの、読み手をぐいぐい引っ張る小説でした。
著者のジェフリー・アーチャーは、自分は作家というよりストーリーテラーだと広言するとおり、二転三転する予想外の展開、張りめぐらされている伏線、語り手を次々に変えていくところなど、読み手を飽きさせることがありません。
ちなみに、作品もおもしろいですが、ジェフリー・アーチャー自身も波瀾万丈の人生を送っている人で、政治家になったり罪に服して刑務所へ行ったり、そしてそういった体験を小説にしたりとなかなかおもしろい人です。
フナツは、アーチャー作品に関しては『百万ドルをとりかえせ』(たしか80年代だと思う・・)からのファンですが、この作品の成立過程自体がまるで小説のようです。
アーチャーは、オックスフォード卒業後、最年少の議員として下院入りを果たしたのですが、詐欺にあって全財産を失い、議員も辞職せざるを得なくなります。そしてその債務を取り返すために小説家に転身し、書いたこの作品がミリオンセラーとなって借金を完済するという、まあなんというかすごい人です。
そのアーチャーが精魂込めて、そして自伝的な要素も含め、長大な「サーガ」(大河小説、年代記、ひとつの家、一門、社会などを歴史的に描く長編小説)を書き上げようとし、この作品がその第一部なのです。おもしろくないわけがない。
この作品はいわゆる「ビルドゥングス・ロマン」(教養小説:自己形成小説、主人公がいろんな体験をしてだんだん大人になっていく過程を描いたもの)です。第一部のこの作品は、主人公が少年から青年になるまでの物語です。
そして「クリフトン年代記」として、1920年から2020年までの100年を舞台にした、一大サーガを書き上げる予定らしく、イギリスではもう第3部まで出版されているそうです。
もうどんでん返しに次ぐどんでん返しで、最後はもうどうにでもして、って感じ終わります。
うーん、続編が翻訳されるのが待ち遠しい・・・。
この作品をきっかけに、いろんなアーチャー作品にふれてみてください。
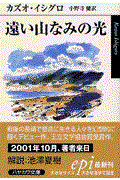
『遠い山なみの光』(2012.8.21 tanakomo)
ちょっと真面目な解説してます。
***
カズオ・イシグロについて少々・・。
たとえば、この本の訳者小野寺健は、彼の作品の根底にあるのは世界を不条理であるとする見方であるとします。ありきたりな言葉でいえば、カフカ的であるということですが、それだけではないと言います。
イシグロにとって、世界は不条理なだけではなく、かすかなものであっても希望を棄てない生き方を描いていると小野寺はあとがきに書いています。つまりイシグロにとって、人生を包む光は、明るい希望の光でもなく、暗い絶望の光でもなく、両者の中間の「薄明」であり、より暗さの勝っている「薄明の世界」ではないかと指摘しています。
そう考えるならば、この本(作家として認められた処女作)では、時代環境の変化を背景にさまざまな犠牲を払いながら成立した女性の自立について書き、二作目『浮世の画家』では戦時中軍に協力した老画家の苦悩を描き、そして三作目の『日の名残り』では、ナチスに協力したことで失意のうちに死んだ貴族に仕えた老執事の、自分の人生についての回想を描いていることなどの、こういった一連の流れについて、カズオ・イシグロを理解するひとつの手がかりがあるように思われます。
さらに小野寺は、このことがイシグロをして、ジョイス、カフカ、ボルヘスといった作家に続く作家たらしめているとまで言っています。
また、池澤夏樹は「日本的心性からの解放」と題した解説において、イシグロが文学は普遍的な人間の心の動きを扱うものであることを信じていること、佐知子はsachikoでもありうることによって、日本文学と英文学といった垣根を飛び越えていると述べています。
さらに池澤のイシグロに関するもうひとつの指摘は、イシグロの作品とはどのようなものであるかを実に的確に表していると言えます。
これは池澤自身の言葉を借りましょう。
カズオ・イシグロは見事に自分を消している。映画でいえば、静かなカメラワークを指示する監督の姿勢に近い。この小説を読みながら小津安二郎の映画を想起するのはさほどむずかしいことではない。特に、旧弊な緒方とそれを疎ましく思っている息子二郎の関係を第三者である悦子の視点から見る描写など、まさに悦子は低い位置に固定されたカメラである。そして、作者のイシグロは更にその悦子の背後にひっそりと隠れている。この自信は無視できない。(272〜273)
上記の池澤の指摘を多少補うなら、イシグロの作品は上質の日本語訳の助けを得ることによって、英語で書かれた日本文学としても成立しうること、そしてそれゆえに日本とイギリスという枠組みを飛び越え、世界文学としても存在しうることを示しているともいえます。
イシグロという才能とその作品を同時代的に体験できる私たちが少なくとも幸運であるといえるのは、日本にしか存在しえなかったかもしれない「日本的心性」というものが、流行りの言葉でいうなら、「グローバル化」によって再輸入され再確認できること、そしてその再確認をすること自体がローカルな世界観に過ぎないということを改めて認識させてくれたということではないでしょうか。
今日は堅苦しい言葉と言い回しですいません。
いずれまた書きます。

『日の名残り』(2012.8.16 tanakomo)
先日来のイギリスつながりではないですが、カズオ・イシグロを読み返しています。
この人の書くものは不思議な味わいがあります。
以前、『わたしを離さないで』をここで紹介しましたが、物語を貫く均質なトーンには並々ならぬ力量を感じます。どこか物悲しく、そして饒舌な、ともするとくどくなりがちな記述や登場人物の心象風景の描写が、決して嫌味にならず、全篇をとおして質の高さを保っているところがすごいです。
実はフナツは学部生時代、文学部英文学科だったのですが(今思うとホントに勉強しない学生だったのですが・・)、その頃嫌というほど読まされた、トマス・ハーディやオースティンや、ジョイス等を(この本を読むと)思い出してしまいます。
あの頃嫌々読んだこれらの作家の作品を現在読むとどう思うのかな、なんてことも考えてしまいました。
個人的にはシャーロット(『ジェーン・エア』書いた人)とエミリ(『嵐が丘』書いた人)のブロンテ姉妹が大好きでしたが、大学では「俗っぽい」と言われた記憶があります。
ま、それはさておき、
この本は、英国最高の文学賞(最近は外国人にも与えられているようですが)受賞作品です。この本を初めて読んだ時には「ブッカー賞がなんぼのもんじゃい」なんて感じで読み始めましたが(日本の芥川賞などの文学賞に飽き飽きしているので)、「うん、これはなんかよくわからないけど、すごい」と読み終えた記憶があります。
そして、いい作品は何度読んでもいいですね。
今回新しい発見がいくつもありました。
実はいろいろ仕掛けがあった・・。
イギリスの田舎(この本に出てくるコーンウォール州方面にはまだ一度も行ったことがない)をドライブしたくなりました。そして舞台となったダーリントン・ホールのようなお屋敷(イギリスではカントリーハウスというそうですが、いわゆる昔の貴族の館で、現在は世界の超お金持ちが所有しているとか、観光施設となって残っているようです)、そういうところも訪ねてみたいなと思います。
ちなみに有名なカントリーハウスとしては、ハリーポッターのあの魔法学校の舞台となった「アニック・カースル」などがあります。
カントリーハウスではないですが、スコットランドの城で「エレン・ドナン城」というのを検索して写真を見てみてください。ハリポタの舞台そのものです。
もちろん、先日アップしたスコットランドとイングランドの戦いの場にも行ってみたいものです。カーライルの街とかスターリング城とか・・。
そして、この本にエピソードとして出てくる戦間期(2つの大戦の間の時期)の外交の裏側などを読むと、改めて近現代史におけるイギリスの政治・経済とか、ヴェルサイユ条約のあたりの外交、特に国際連盟におけるイギリス指導層の役割とかをもう一度じっくり調べてみたいという気にもなりました。(いちおうフナツは新渡戸稲造で論文を書いたので、国際連盟とその周辺にはちょっとうるさい)
ま、それもさておき、
うーん、でもこの本の魅力をどう伝えようかと悩んでしまいます。
まず、主人公は「執事」(バトラー、butler)です。「他の国にも「召使い」はいるが、執事がいるのはイギリスだけだ」とはよく言われる言葉です。
イギリスにおける執事のふるまいや仕事ぶり、さらに20世紀初め頃のイギリス(「大英帝国」が滅びつつある頃)のアッパークラスやアッパーミドルの人々がどのような話し方を好んだのか、そしてジェントルマンというのはどのような人種なのか、そんなイギリス関連のいろんなことがわかっているととてもおもしろく読めるし、反対に、そんなことまったく知らなくてもこの本でそういうものだったのかと知ることができます。
あー、こんなこと書いても全然この本の魅力を伝えられないですね。
でも、万人受けする小説でもない、とこれははっきりいえます。
ストーリーの面白さとか、わくわくする謎解きなどという要素からはおよそ遠い小説です。
淡々と語られていく主人公のさまざまな回想、時系列は後になり先になり、さらに関連のなさそうなエピソードが実に巧みに組み合わされ、物語を形作っていきます。
加えて、大事なことをさらりと書くんですね、イシグロさんは。
まあ、内容の説明はサイトをクリックして読んでもらうとして、物語の切なさや、最後の日、ベンチの隣に座った男のセリフ「夕方が最高さ」とか、大英帝国の黄昏か、さらに、この本の題名ってなんだったっけ、などなどを味わって頂ければと思います。
いい小説は読後感がいいですね。
あ、でもカズオ・イシグロをまだ全然読んでない人は、まずは『わたしを離さないで』から読んだほうがいいかもしれません。
さて、スティーブンスの語り口を真似るなら、
「これ以上お話をいたしますと、みなさまのこの本を読む楽しみをわたくしが奪いかねません、わたくしはこのあたりで失礼させていただきとうございます」
カズオ・イシグロさんに関しては書きたいことがたくさんあるので、また別の機会に。
あー、それから、最後にある丸谷才一さんの解説は小説を読んでから読んだ方がいいです、念のため。

『世界のすべての7月』(2012.2.13 tanakomo)
この本は好き嫌いが分かれるだろうなと思います。
でも、先日紹介したカズオ・イシグロを読んで「翻訳物もけっこういいじゃん」と好きになり、村上春樹も決して嫌いではないという人なら楽しめるんじゃないかなと思って紹介します。決して感動大作っていうんじゃないです。淡々と、でもなんとなく引き込まれて、って感じの小説です。
ムラカミさんは訳者あとがきで彼の魅力をこんなふうに述べてます。
***
お読みになっていただければわかるように、『世界のすべての七月』は群像劇である。様々な過去を背負った人々が大学の同窓会に集まり、そこで一人ひとりの物語が語られていく。六十年代に波瀾万丈の、あるいは華やかな青春を送った人々も。今や五十代半ばを迎え、それぞれに人生に幻滅し、企てに挫折し、精神的にすり減り、それでもなんとか人生を仕切り直し、モラルや目的を立て直そうと試みている。決して見通しは明るくないけれど(そして何人かは既に人生を唐突に終えてしまったけれど)、それでもそこには決然とした「集合的意欲」のようなものがうかがえる。そして人々は生き続けるために、燃料としての記憶を切実に必要としている。
(中略)
しかしオブライエンは、その再会物語を決してセンチメンタルに、整合的に、「よくできた話」として描こうとしてはいない。そのへんが凡百の作家とは違うところだ。彼はむしろ、どたばた劇として、延々と続く笑劇(ファルス)として、この長編物語を成立させている。まとまりよりは、ばらけの中に真実を見いだそうとしている。解決よりは、より深い迷宮化の中に、光明を見いだそうとしている。明るい展望よりは、よたよたとしたもたつきの中に希望を見いだそうとしている。もちろん思い入れはある。しかしその思い入れは、多くの場合空回りしていて、読んでいてなんとなく面はゆく感じられてしまう。もちろんそれは意図的なものであり、決して作家が下手だからではないのだけれど、なんとなくそれが下手っぴいさに思えてしまうところが、オブライエンの小説家としての徳のようなものではないかと、僕は思う。つまり、それが偉そうな仕掛けに見えないところが、実はこの小説のいちばんすごいところなのかもしれない。
ただ翻訳者としては、この小説が若い世代の読者にどのように受け入れられるのか、もうひとつ自信がない。僕自身はオブライエンとほぼ同世代なので、読んでいて「うんうん、気持ちはわかるよ」というところはある。世代的共感。五十代半ばになっても行き惑い、生き惑う心持ちが実感として理解できるわけだ。でも、たとえば今二十歳の読者がこの小説を読んで、どのような印象を持ち、感想を持つのか、僕にはわからない。「えー、うちのお父さんの歳の人って、まだこんなにぐじぐじしたことやってるわけ?」と驚くのだろうか?
***
少しはこの小説の魅力が伝わりましたか??
でもよくできた小説を読むって楽しいですよね。
たとえば知の巨人として知られる立花隆さんは「僕は小説、フィクションの類いは読まない。所詮フィクションは作り物に過ぎないし、現実のほうがよほどおもしろい。だから僕はノンフィクションしか読みません」とおっしゃってます。他にも同様のことを話しておられる(偉い)方々も現実にいらっしゃいます。
でも凡人のフナツにとってはフィクションがおもしろい。現実よりも作り物でいい。違う世界に連れて行ってくれて楽しませてくれる小説がいいと思ってます。

『私を離さないで』(2012.1.12 tanakomo)
とても不思議な物語です。ミステリの要素もあり、ネタばらしはいけないというところもあり、でもそれがわかっていても引き込まれる魅力があり、叙情豊かにある学校の青春物語が描かれていて、でも実はとても残酷な物語で、って魅力を語りだすとネタばらしになってしまうのでやめます。
決して気持ちの悪い小説ではありません。「残酷」といっても暴力や性的描写、イジメみたいなものが書かれているわけでもありません(フナツはそういう小説は読まないので)。読後、不思議な悲しみ、透明感のある寂しさに包まれてしまう(あー、書いててもどかしい、「何なんだよ、透明感のある寂しさ」ってよぉ、なんて言われそう)小説です。
カズオ・イシグロ入門としてはいい本です。
あー、ちなみに、カズオ・イシグロは血は日本人ですが、イギリスで育ち、英語で小説を書き、さまざまな賞をもらっている人です。ここで紹介した本は日本語に翻訳されたものです(ちなみに、このアドレスは単行本の紹介ですが、文庫本も出ているのでそちらのほうを)。そう、その英語で書かれた原書の方を英語の授業で読もうじゃないか、という話を今日していたのです。
好みは分かれるかもしれませんが、ノンフィクションやビジネスの本の書き込みが最近増えていたので、久しぶりに「文学」を。

『マネーボール』(2011.10.7 tanakomo)
今日は映画の原作本の紹介です。(日本で翻訳が出たのは2004年ですが)
2000年に入ってからの大リーグで、ヤンキース(余談ですが、英語で読むときはヤンキー「ズ」です、念のため)やレッドソックス(こちらは「ス」でいいです)のように資金が潤沢なチームが強いのは当然だけど、田舎の弱小貧乏球団(失礼!)であるオークランド・アスレチックスがなぜかそこそこ強い。強いチームはお金をかけて、いい選手を確保し、そうでないチームは弱いという経済的法則があったわけですが、アスレチックスだけは投資効果が抜群にいい。ほとんどお金をかけてないのに、まずまずの結果を残している、いったなぜ?というところから話は始まります。それはビリー・ビーンGMのこれまでの野球界の常識を覆すような手法だったのです。ってどんな手法かは読んでのお楽しみ。おもしろいです!!
